合格圏にいても縁がないこともある
きただです。 合格圏にいても、その大学・高校に縁がないこともあります。 A判定だったのに、不合格などはその最たる例です。 受からなくべくして受からない人 のではなく、受かるべくして受からないこのような...
2026年02月22日大牟田市・オンラインで完全個別指導・少人数個別指導の英語塾・進学塾・有明高専生専門塾を運営しているきただです。
よくいただくご相談の一つに
「勉強のやる気が出ません」
「子供が勉強しないのですが、どのようにするといいでしょうか」
など、やる気やモチベーションについてがあります。
そもそも、大前提としてやる気やモチベーションに頼って勉強してはいけません。
モチベーションに続かないからです。
一番危険なのが、一気にやる気が出た時ですね…
上がったやる気は必ず下がりますから。
こんな経験ないでしょうか?
「勉強のやる気が出たと思った次の日には、全くやる気がなくなっている」
上がったやる気は寝たらフラットになります…
前提として、やる気に頼って勉強してはいけないというのはあるのですが、まずそもそもなぜやる気が出ないのか、勉強のやる気が出ない原因や、モチベーションをアップさせるための具体的な方法を科学的根拠に基づいて徹底解説します。
中学生・高校生が勉強に対してやる気を失うのはなぜか、その背後にある脳の働きや生活習慣の問題を明らかにし、誰でも実践できる対策を紹介しています。
勉強に悩む学生やその保護者に向けた、すぐに役立つ内容だと思います。
ちなみに、本記事では一般的に言われていることをまとめているだけです。
僕オリジナル方法はブログではあまり公開していません☺︎
勉強のやる気がなくなるのは「気持ちの問題」だけではありません。
脳の中でどのような化学反応が起こっているのかを知ることで、やる気の低下を理解し、どうすればモチベーションを回復できるかが見えてきます。この章では、やる気と密接に関わる「神経伝達物質」について解説します。
ドーパミンとは、脳内で分泌される神経伝達物質の一つで、やる気やモチベーションに深く関わっています。たとえば、試験勉強で問題を解けたときや、新しい知識を理解できたときに、私たちの脳は「報酬」としてドーパミンを放出します。このとき、私たちは達成感や満足感を感じ、それが次のやる気を生み出すきっかけになるのです。
もしドーパミンの分泌が少なかったり、脳内でうまく働いていなかったりすると、勉強の達成感が得られず、モチベーションが低下しやすくなります。つまり、ドーパミンは、勉強を続けるための「やる気エンジン」のような役割を果たしているのです。
特にゲーム・スマホ・SNS・漫画などが脳の報酬系をバグらせて、やる気を出にくくさせます。
セロトニンは、心の安定や気分を整える働きがある神経伝達物質です。セロトニンの分泌が十分であれば、私たちはリラックスした気分で、安定して勉強に取り組むことができます。
しかし、セロトニンが不足していると、イライラしたり、集中力が散漫になりやすく、結果として勉強に対するモチベーションも低下してしまいます。
このセロトニンの分泌量は、主に睡眠や食事のリズムによって左右されます。特に、夜遅くまで勉強をして睡眠不足になったり、食生活が乱れたりすると、セロトニンのバランスが崩れてしまい、勉強へのやる気が一気に失われる原因になるのです。
ちなみにセロトニンはぬいぐるみ抱いて寝てると分泌されますよ笑…
あと、動物と触れ合うのもいいですね。
試験や宿題、親や先生からの期待など、日常的なストレスは、脳の神経伝達物質に大きな影響を与えます。ストレスを感じると、体は「コルチゾール」というホルモンを分泌します。
このコルチゾールは、ドーパミンやセロトニンのバランスを崩し、結果的にやる気を低下させてしまいます。
また、ストレスが長期間続くと、脳は慢性的な疲労状態に陥り、集中力や判断力も低下してしまいます。
これを防ぐためには、定期的にリラックスする時間を設けたり、友達と楽しい時間を過ごすなど、ストレスを解消する方法を取り入れることが大切です。
ただ、一概にコルチゾールが悪いわけではありません。
コルチゾールは起床の1時間前から分泌され、快適な目覚めを助けてくれます。また、コルチゾールはメラトニンに変換され、このメラトニンの量が良質な睡眠へ導くのです。
やる気を持続させるためには、明確で現実的な目標設定が重要です。目標が曖昧だと、勉強の進捗がわかりにくく、達成感を得られないため、モチベーションが続きません。
この章では、やる気を引き出す効果的な目標設定の方法について説明します。
ちなみに私はこのモチベーション方法ではなく、〇〇〇〇モチベーションという方法を使っています。これも本邦非公開です☺︎
SMARTとは、以下の5つの要素を満たす目標設定のことを指します:
目標設定法はさまざまな方法がありますので、あくまでも一例を書いています。
自分に合った方法を見つけるといいでしょう。
勉強の目標が大きすぎると、達成するまでに時間がかかり、その過程で挫折しやすくなります。そのため、まずは小さな目標を設定し、それをクリアするたびに達成感を得られるようにすることが重要です。
たとえば、1時間勉強したら10分間休憩する、といったように、短いサイクルで小さな成功体験を積み重ねることで、モチベーションを保ちやすくなります。
こうした「成功体験」が積み重なると、脳が「勉強は達成可能なものだ」と認識し、次のステップに進むためのやる気を生み出します。
自分に対して過度な期待をかけると、「うまくできないかもしれない」「失敗するかもしれない」という不安が強くなり、結果としてやる気を失ってしまうことがあります。これは、自己効力感(自分が目標を達成できるという自信)が低下するためです。
自己効力感(じここうりょくかん)とは、簡単に言うと「自分が目標を達成できると信じる気持ち」のことです。心理学者アルバート・バンデューラが提唱した概念で、「自分の行動や努力が結果に結びつく」と信じられるかどうかが、自己効力感に関わっています。
過度なプレッシャーをかけずに、現実的な目標を設定することで、自己効力感を高め、モチベーションを持続させることが可能になります。
勉強のやる気は、心理的な要因だけでなく、日々の生活習慣とも深く関連しています。特に、睡眠や栄養がモチベーションに与える影響は大きく、これらの習慣を整えることがやる気を保つための重要な鍵となります。
あとは、腸内環境やメンタルヘルスも大事だったり…ここは割愛します。
睡眠不足は、脳の働きを著しく低下させる原因の一つです。十分な睡眠が取れていないと、脳は疲れやすくなり、集中力が低下します。結果的に、勉強に対するやる気も失われがちです。
特に、成長期の中学生や高校生にとっては、1日6~8時間の質の高い睡眠が必要です。勉強の前日は早めに寝るよう心がけることで、翌日にはすっきりとした気分で勉強に取り組むことができます。
寝なさすぎも良くないですし、寝過ぎも良くないです。
また、スヌーズ起きや起床時間が固定されないのも、体内時計が狂うくらおすすめしません。
先日、夜中の激しい雷雨で夜中に何度も起こされ、体内時計が狂いました。その結果、一日中マインドフォッグの状態(意識混濁)になりました。
本当に…睡眠の質が1日のパフォーマンスを変えます。
脳の働きをサポートするためには、ビタミンB群やマグネシウム、オメガ3脂肪酸などの栄養素が不可欠です。これらの栄養素が不足すると、脳が疲れやすくなり、やる気を維持するのが難しくなります。
特に、食事が偏っている場合は、脳に必要な栄養が十分に供給されず、勉強中に集中力が途切れたり、疲労感を感じやすくなります。バランスの取れた食事を意識し、日々の食生活を整えることが、モチベーション維持の秘訣です。
僕の場合はサプリメントで日々必要な栄養素を補っています。
あとはどの食べ物を何時に食べるかでも1日のモチベーションというかぱパフォーマンスが変わってきます。
適度な運動は、脳内の神経伝達物質を活性化させ、ストレスを軽減し、勉強に対するやる気を高める効果があります。
特に、軽いウォーキングやストレッチを日常的に取り入れることで、血流が良くなり、脳への酸素供給が促進されます。これにより、集中力が増し、勉強に取り組む意欲も高まるのです。
ガッツリ運動する必要はなく、勉強の合間にスクワットなど筋肉量が大きい部分を動かすトレーニングを入れるといいですよ。
またウォーキングはストレス軽減効果がありますのでメンタルヘルスの意地に効果的です。森林の中でのウォーキングはさらにストレス軽減効果が高まります。
やる気が出ない原因とその対策を科学的に理解し、モチベーションを高めるための具体的な方法を取り入れることで、勉強に前向きに取り組むことができるようになります。
日々の勉強において、科学的な根拠に基づいたモチベーションアップ法を実践することで、やる気を持続させることができます。ドーパミンやセロトニンといった神経伝達物質の役割を理解し、適切な目標設定や生活習慣の改善を取り入れることで、勉強に対する意欲が自然と湧いてくるでしょう。
本記事が皆様のご参考になれば幸いです。

きただです。 合格圏にいても、その大学・高校に縁がないこともあります。 A判定だったのに、不合格などはその最たる例です。 受からなくべくして受からない人 のではなく、受かるべくして受からないこのような...
2026年02月22日
きただです。 少しセンスティブな記事になってしまいますが、当塾ができる合理的配慮について書きたいと思います。 実はきただは ・不登校 / 通級を経験している生徒・発達障害(ASD・ADHD・学習障害な...
2026年02月19日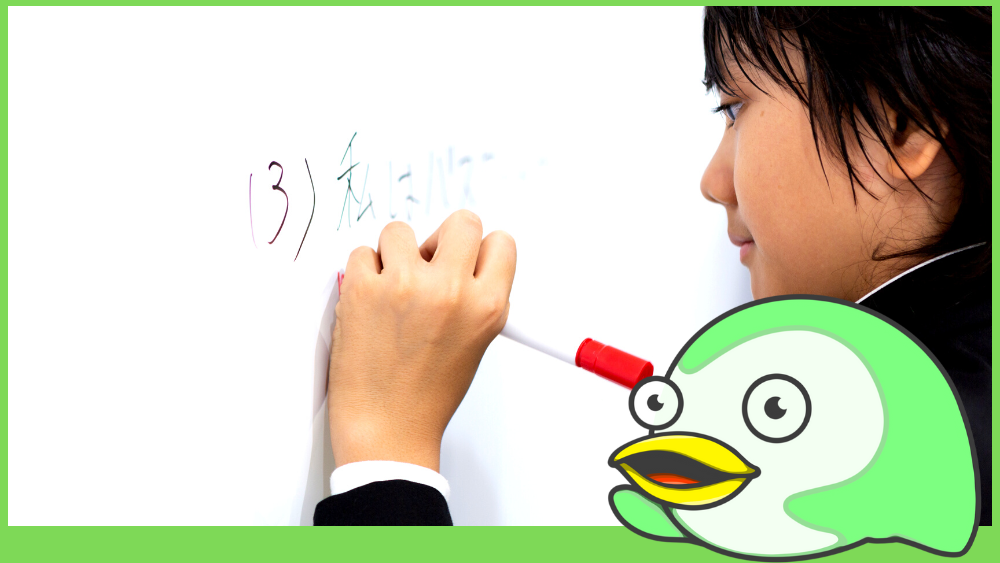
きただです。 塾屋さんの僕は勉強だけしかしていないと思われていますが、 筋トレやピラティスもしています。 (好きなトレーニングメニューはブルガリアンスクワットとルーマニアンデッドリフトです。) 筋トレ...
2026年02月12日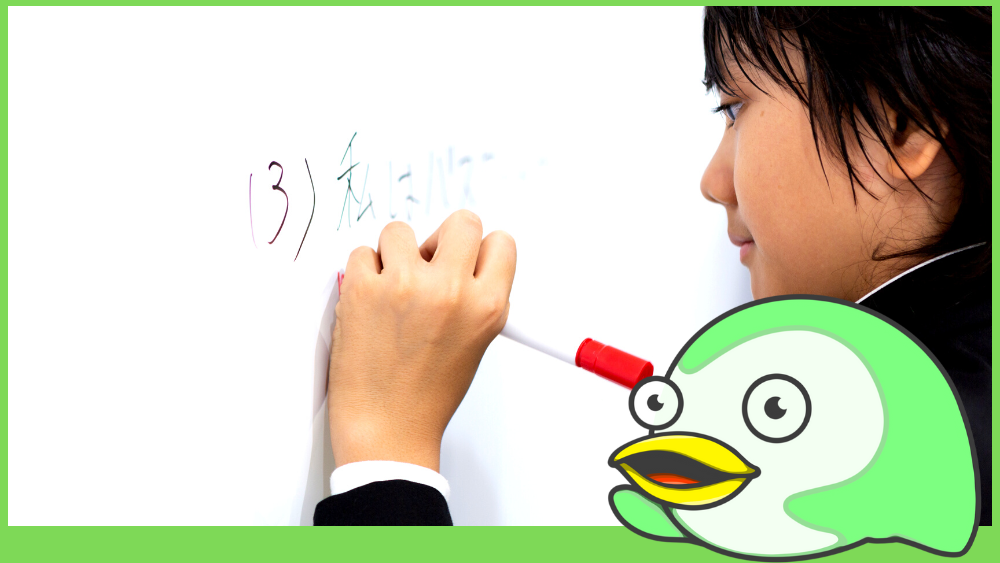
きただです。 もうすぐ福岡県公立高校の特色化選抜・推薦の合格発表ですね。 まだ、合格発表もまだの状態でこれをいうのは躊躇われますが、言っておきます。 高校受験の合格はゴールではありません。ここからが本...
2026年02月06日