ご卒塾・ご退塾について
きただです。 卒塾のシーズンとなりました。 卒塾をご検討されいているご家庭も増えてきているかと思いますので、卒塾についての考えを記事にしました。 結論、 当塾では、在塾期間について特に期限を設けていま...
2026年01月08日こんにちは、きただです。
生徒や保護者の方からよく聞くお悩みに、こんなものがあります。
「うちの子、家でも塾でもそれなりに頑張ってるのに、なんで成績が上がらないんでしょうか?」
このようなケース、実は非常に多いです。
そしてその原因は、「勉強時間が少ないから」だけではありません。
今回は、成績が上がらない原因を8つに分けて詳しく解説します。
特に後半では、発達障害や精神疾患など“見えにくい要因”にも触れていきます。
意外と多いのが、「学校の授業をしっかり聞けていない」こと。
集中力が続かない/先生の話が頭に入っていない/ノートだけ写して満足、などが積み重なると、塾や自宅での学習効率も大幅に下がります。
よく塾生に伝えるのが、
「学校の授業中に思考停止になっていない? 塾の先生が教えてくれるから、わからなんでもいいや状態では、その分の補習を自分でしないといけないんだよ」
です。
授業中の思考停止は極力減らしましょう。
ただ「読んでいるだけ」「暗記カードをながめているだけ」「問題集を1周で終えてしまう」など、努力の方向がズレているケースも多いです。
あとは、要領の良さも大切です。
1時間で5ページ進むのか、1時間で1ページ進むのかでは学習効率が全く違います。
〇〇時間勉強しただけではなくて、どれくらい進んだのかも大切ですよ。
「わかる」と「できる」は違います。
演習を繰り返さないと、本番の問題で手が動かなくなります。
まず、成績をあげたいなら、勉強時間や演習量を伸ばすのが最初にやって欲しいことになります。
あとは、
生まれた時から勉強しているのか高校生になって勉強を頑張り始めたのかでも違います。
スポーツも同じですよね。
生まれた時からそのスポーツに触れているのか、それとも中学生からそのスポーツを始めたのかでは差が大きいですよね。
勉強もそれと同じですよ。
成績の良い生徒は、自然と「なぜそうなるか」「他とどう違うか」を考える癖がついています。
一方で、成績が伸び悩む生徒は全てを丸暗記をし、問題の類似性などを見抜けません。
特に高校生以上で成績が伸び悩むタイプはここに該当します。
「間違えたくないから手が出ない」
「どうせやってもムダだと思ってしまう」
こうした思考のクセは、努力や知識以前に成績のブレーキになります。
ここら辺は時間をかけて成功体験を積んでいくしかないです。
以下のような特性が強く見られる場合、「努力の質」では解決しにくい壁が存在します。
高校受験で合理的配慮を求めての受験が可能ですよ。
中高生の中には、うつ病や不安障害、起立性調節障害(OD)など、見えにくい精神的な問題を抱えている子もいます。
これらは「甘え」ではなく、心と身体の不調である可能性があります。
特に精神的不安感は女子生徒に多い傾向があります。
精神疾患は気づかれにくいですが、対応が遅れると勉強どころではなくなります。
「いつもと違うな」と感じたときは、塾としてもご家庭と連携しながら見守ります。
「成績の6割は遺伝で決まる」という研究報告もあります(英・キングスカレッジ他)。
たとえばIQ、処理速度、性格(粘り強さ・衝動性)などが影響します。
とはいえ、「遺伝=どうにもならない」ではありません。
環境と努力次第で差は十分に縮められます。
自分が伸ばせる最大値を目指して努力する
これがとても大切だと思います。
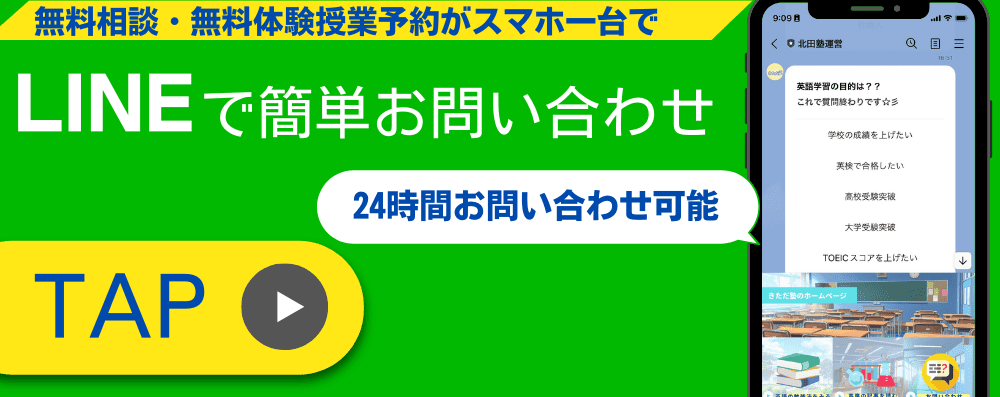

きただです。 卒塾のシーズンとなりました。 卒塾をご検討されいているご家庭も増えてきているかと思いますので、卒塾についての考えを記事にしました。 結論、 当塾では、在塾期間について特に期限を設けていま...
2026年01月08日
きただです。 近ごろ、当塾へ 小学1〜3年生のお子さまをお持ちの保護者様 からのご相談が続いています。 「今のうちから何か始めた方がいいのか」「勉強の土台づくりが心配で…」 そんなお声をいただくたびに...
2026年01月07日
きただです。 有明高専の推薦選抜が1月10日(土曜日)に実施されます。 2026年度(令和8年)の推薦選抜志願者数は155名 (67) ()は女子の人数です。 例年より10名~20名ほど少ない志願者数...
2026年01月03日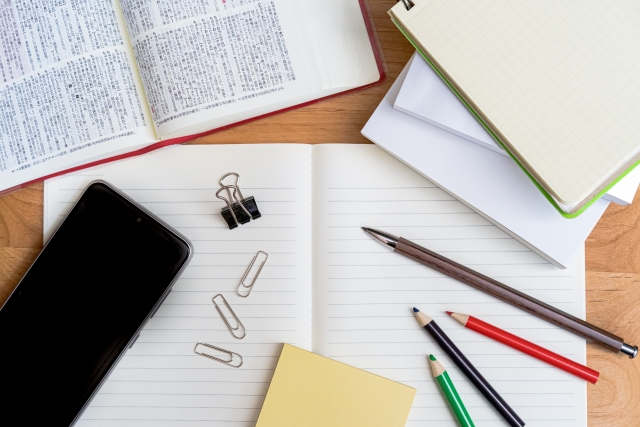
きただです。 年末ですので2025年を振り返りをしようかと思います。 備忘録ですので特に有益な情報はございません。悪しからず。 塾として大きな変化は三つありました。 ① 公立 / 私立進学校に通う塾生...
2025年12月23日