合格圏にいても縁がないこともある
きただです。 合格圏にいても、その大学・高校に縁がないこともあります。 A判定だったのに、不合格などはその最たる例です。 受からなくべくして受からない人 のではなく、受かるべくして受からないこのような...
2026年02月22日本記事はこのような疑問や悩みについて解決する記事です。

まずは多読についてです。
多読は私自身が英語脳を作るきっかけになった英語学習法で、英語学習初期段階から取り入れ始めました。
多読とは、洋書・絵本・雑誌・記事・webサイトを英語で理解しながらたくさん読んでいく英語学習法です。
日本の英語教育で行われている翻訳をするプロセスを一切通さず、
多量の英語を読むことから英語を英語で理解する英語脳の形成と英語の語感を身につけることができます。
英語脳が強ければ強いほど、リーディング、ライティングスピーキング、リスニングのレベルも上がっていきます。
(英語脳は鍛えるものなので、強いという表現をここでは用いています。)
どの言語もそうですが、インプットの量が多量であれば、あるほど言語力が優れる傾向にあります。それは日本語でも英語でも同じです。
早いスピードのリスニング音源を用いてリスニングをやり続けると、英語を英語のまま理解できる能力が身に付きます。
リーディングは、自分自身が読む速さを調節することができます。
そのため読む速さが遅いと翻訳してしまったり、返り読みをたくさんしてしまいます。
それでは、英語脳を鍛えることができません。
対して、リスニングの速度はその教材・スピーカーに依存します。
つまり、英語の処理量を自分でコントロールすることができません。
音源はどんどん流れてきますので、翻訳する時間もありませんし、返り読みする時間もありません。
ですので、
翻訳する時間も返り読みする暇もないくらいの音源でリスニング練習を続けると、翻訳癖や返り読みの癖がなくなり、英語を英語で理解できるようになります。
これがリスニングで英語脳が作れる理由です。
リスニングを鍛える方法にもいくつかの種類がありますが、
英語脳を作る学習法としては、
多聴
をおすすめします。(英語脳を作る場合においては)
多聴とは、自分の英語力で7~8割聞き取れる音源を多量に聞く英語学習法です。
英語のスクリプトなしで7~8割できる素材を使って行いましょう。
英語脳を強制的に作っていくには、
環境を自ら作っていくことも大切です。
翻訳癖や返り読みをする癖があると、英文をみると脳が勝手に翻訳処理を始めてしまいます。
そんな時間を脳にあたえない。
それくらいの速度で英語を読む練習をすると、いつの間にか翻訳癖や返り読みの癖がなくなります。
※多読初期時は、勝手に脳が翻訳を始めてしまいますので、速読も同時に行なっていもいいかもしれません。
音読も英語脳を作ることができる英語学習法の一つです。
一つのリーディング素材で音読を30回以上繰り返す。
これを繰り返していくと、英語の語順で英語を理解できるようになります。

のプロセスを非効率だと判断します。
日本語を介するだけで、脳の負担がものすごくかかります。
(多くの英語学習者がTOEICで疲れるのは、日本語に介して大量の英語を読んだり聞いたりしているから)
脳が日本語に介して英語を理解することは非効率だと判断すると、
英語を英語で理解する癖がつき始めます。
留学しても英語に触れる機会を自ら作らなければ英語は伸びません。
日本で英語を勉強しない人が留学しても一からの英語学習になりますので、相当しんどいです。
もし留学を考えている人は今のうちに英語のレベルを上げておきましょう。
英語脳を作るための英語学習法を4つを紹介しました。(留学は英語学手法ではなく、機会)
英語学習法は相性が肝心ですので、もし英語脳を作りたいのであれば、
試してみて相性がいい学習法で英語脳を作るといいでしょう。
ここまでお読みいただきありがとうございました。

きただです。 合格圏にいても、その大学・高校に縁がないこともあります。 A判定だったのに、不合格などはその最たる例です。 受からなくべくして受からない人 のではなく、受かるべくして受からないこのような...
2026年02月22日
きただです。 少しセンスティブな記事になってしまいますが、当塾ができる合理的配慮について書きたいと思います。 実はきただは ・不登校 / 通級を経験している生徒・発達障害(ASD・ADHD・学習障害な...
2026年02月19日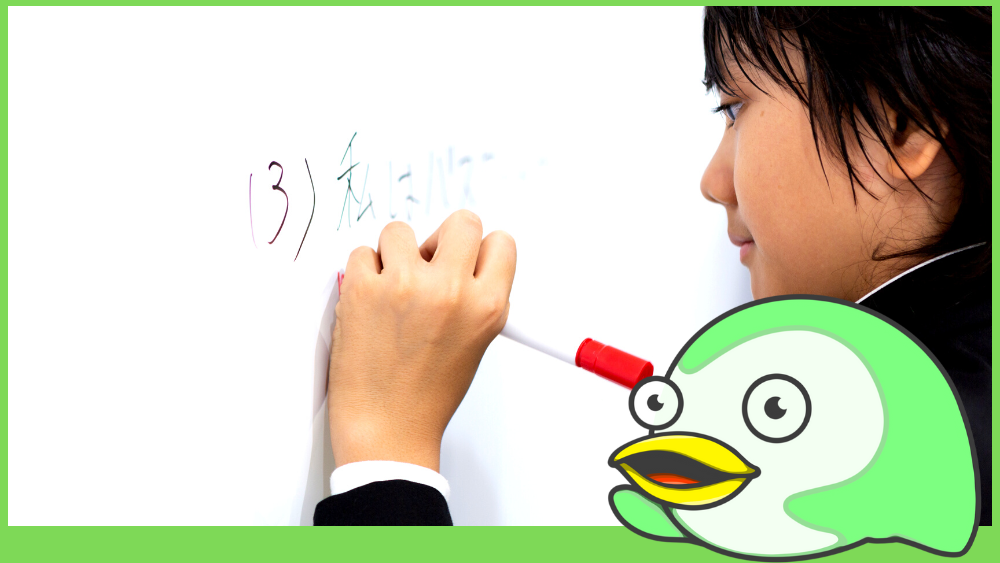
きただです。 塾屋さんの僕は勉強だけしかしていないと思われていますが、 筋トレやピラティスもしています。 (好きなトレーニングメニューはブルガリアンスクワットとルーマニアンデッドリフトです。) 筋トレ...
2026年02月12日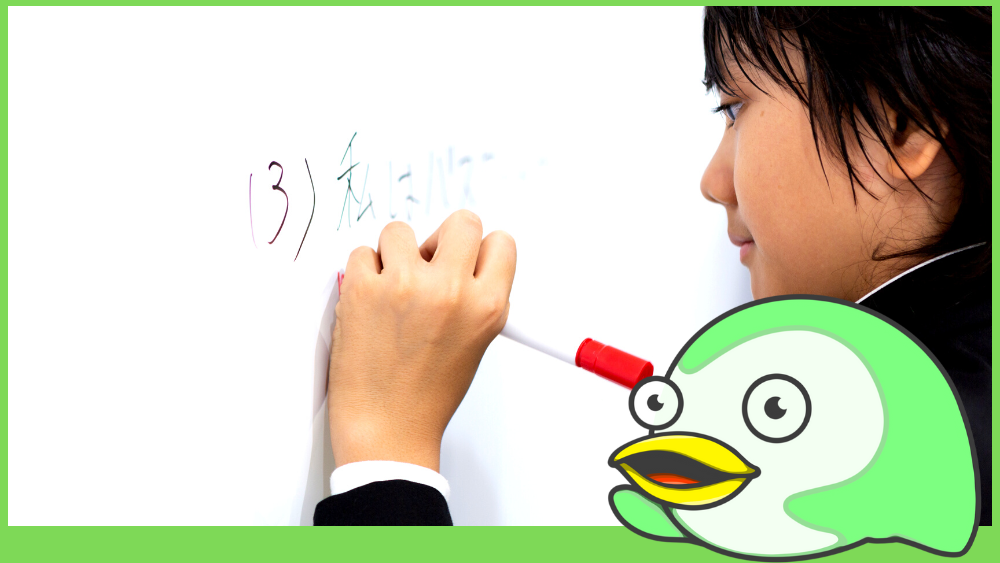
きただです。 もうすぐ福岡県公立高校の特色化選抜・推薦の合格発表ですね。 まだ、合格発表もまだの状態でこれをいうのは躊躇われますが、言っておきます。 高校受験の合格はゴールではありません。ここからが本...
2026年02月06日